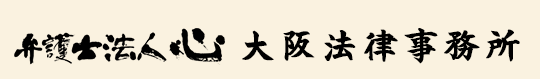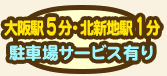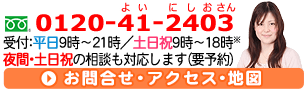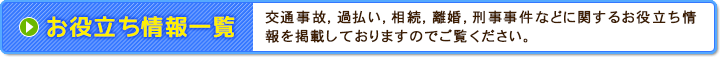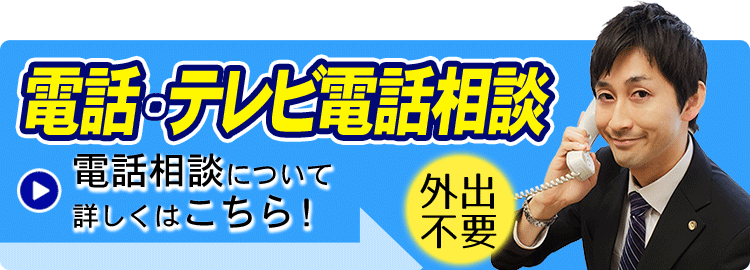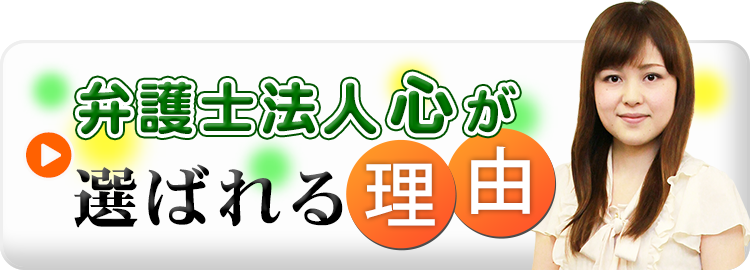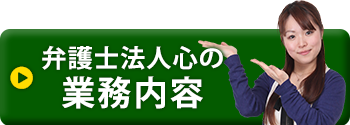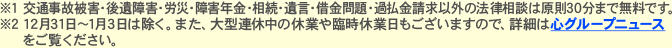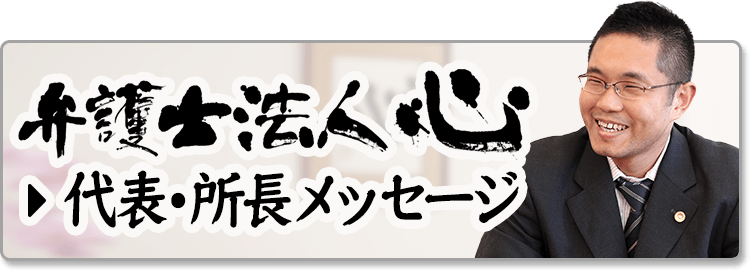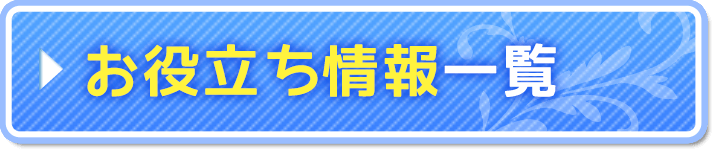初診日の証明方法とは?
1 受診状況等証明書による証明
初診日は、原則として、受診状況等証明書という書式を利用して証明します。
受診状況等証明書は、どこの病院で書いてもらったものでもよいというわけではありません。
初診日に通院した病院に、受診状況等証明書の作成を依頼して書いてもらうことで、初診日の証明が可能となります。
受診状況等証明書の書式は年金事務所で交付してもらうこともできますし、インターネット上で行政のホームページから印刷することもできます。
また、弁護士や社会保険労務士などの専門家に依頼していただいた場合には、受診状況等証明書の書式は専門家の方で用意することが可能です。
2 受診状況等証明書を取得できない場合
初診でかかった病院が閉院してしまっている場合や、長期間通院していなかったためカルテ等の医療記録が廃棄されてしまって、初診日の確認ができなくなってしまった場合には、初診の病院で受診状況等証明書を作成してもらうことができません。
このような場合には、どうして初診の病院で受診状況等証明書を取得することができないのか、理由や経緯を説明した書式を年金事務所に提出する必要がございます。
そして、そのうえで、受診状況等証明書以外の方法で、初診日を証明する必要がございます。
例えば、初診の病院では記録がなくなっているため初診日の確認ができなかったものの、2番目にかかった病院に、初診の病院からの紹介状が残っていて、それによって初診の日付が確認できる場合などには、その紹介状を提出することで初診日の証明とすることが可能です。
また、5年以上昔のカルテの記載中に、初診日についての記載があった場合には、それらの記録も初診日の証明に利用することができます。
こういった、2番目以降にかかった病院の医療記録から、初診日を確認することもできない場合には、その他の資料を集めて証明するしかありません。
例えば、診察券やお薬手帳の記録、病院に通院していた際の領収書等の資料を集めて、初診日の証明ができる場合もあります。
また、労災や障害手帳、生命保険の請求などに利用した診断書などの資料が残っている場合にはそれらも証拠資料となりえます。
また、そういった資料が全く用意できない場合でも、知人などの中立的な立場の第三者に、初診日について証言をしてもらうことで、初診日の証明ができる場合もあります。
これを第三者証明といいます。
例えば、初診日当時の勤務先の上司などに、その当時、どういった病気でどういう病院に通院したと報告をうけたことがあるといった証言をしてもらえる場合などが、第三者証明の典型的な事例です。
3 幅を持たせた初診日の特定
最後に、初診日の証明について、完全に特定の日付までは証明できないけれども、一定の期間内に初診日があることは証明できるというような場合もあります。
例えば、2002年秋の健康診断で数値の異常値を指摘されて、その後個人の開業医が経営するA病院で初診の受診をして、1週間程で精密検査が必要といわれて大病院Bに転院したというような場合を想定します。
このような場合で、健康診断の結果は記録として残っていて、さらに2件目の病院Bのカルテの中に、2002年秋の健康診断で異常値を指摘されてA病院から紹介されて来院したことは記録されているものの、A病院の具体的な初診の日付までは記載されていないとします。
このような場合で、A病院がすでに廃院になっているためA病院に受診状況等証明書の作成を依頼できないとすると、具体的に日付を特定して初診日を証明することはできません。
しかし、2002年の秋の健康診断から大病院Bを受診するまでのどこかで、A病院の初診があることは、大病院Bのカルテから確認ができています。
そうすると、「健康診断から大病院Bの受診までのどこか」という範囲で初診日を特定することになります。
このように幅を持たせた初診日の特定でも、その幅のどこをとらえて年金の納付要件を満たしているような場合には、年金申請が認めらえる可能性があります。
学生でも障害年金の支給を受けられますか? 現在依頼している弁護士と意見が合わないのですが、どうしたらいいですか?