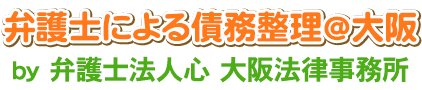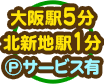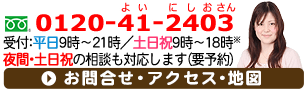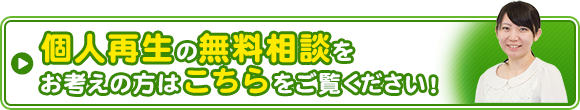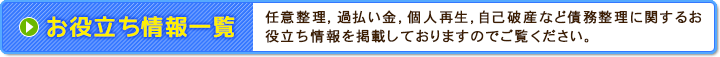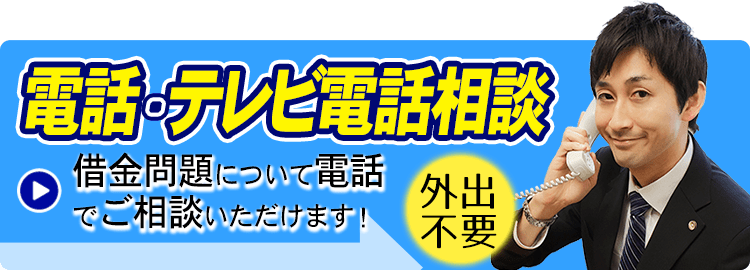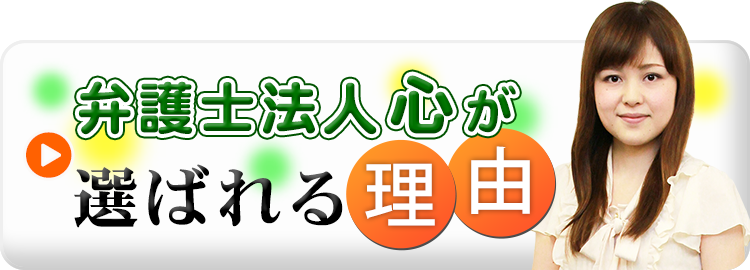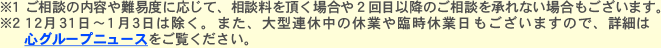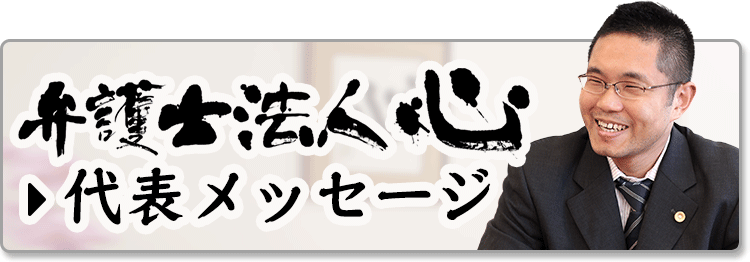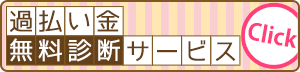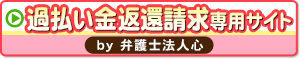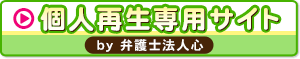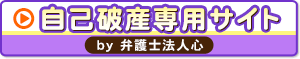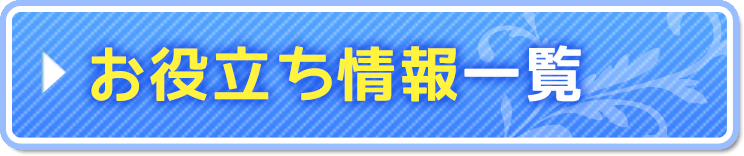「個人再生」に関するQ&A
住宅がアンダーローンとなっているのですが個人再生できますか?
1 ハードルは高くなります
住宅がアンダーローンとなっている場合でも、それだけで個人再生ができなくなるわけではありません。
ただし、住宅ローンが住宅価格を上回る、いわゆるオーバーローンの状況に比べると、個人再生が認められるためのハードルは高くなります。
以下に、その詳細をご説明します。
キーワードとなるのは、清算価値保障原則です。
2 清算価値保障原則とは
まず、個人再生を行う場合、どうして住宅がアンダーローンかオーバーローンかが重要になるのかについて知る必要があります。
ここで問題になるのが、冒頭で紹介した清算価値保障原則という考え方です。
清算価値とは、簡単に言い換えると、「いまもし破産することになったら、債権者に分配できる財産がいくらあるか?」ということです。
例えば、債務額の合計500万円以下の方が個人再生をした場合、個人再生の法律上の弁済額の最低ラインは100万円になります。
この方が、仮に自己破産をすれば300万円は債権者に配当できる財産を持っていた場合、債権者からすれば100万円まで受け取れる金額が減ってしまう個人再生に賛成するぐらいなら、自己破産をするように希望するはずです。
そのため、個人再生では、清算価値(自己破産をした場合に債権者に配当できる財産の合計額)より、低い金額には減額しないという制限がかけられています。
このような制限のことを、清算価値保障原則と呼びます。
3 アンダーローンが個人再生に与える影響
住宅ローン特別条項を利用して、住宅を残すタイプの個人再生をする場合、住宅を財産として所有している状況で個人再生をすることになるため、住宅価格が財産目録に計上されることになります。
ただし、清算価値はあくまで自己破産をした場合に、いくら債権者に配当できるかという話です。
そのため、住宅に住宅ローン会社の抵当権がつけられている場合には、自己破産をしてもまずは住宅ローン会社が優先的に支払いを受けることになります。
住宅ローン会社以外の債権者に配当がされるのは、住宅ローンを支払ってもなお余りが出る価格で住宅が売れた場合だけです。
そのため、住宅ローンの残高が住宅価格を上回るオーバーローンの場合には、清算価値は0円で計算されることになるので、住宅があってもなくても個人再生の返済額に影響はないことになります。
反対に、住宅ローンの残高が住宅価格を下回るアンダーローンの場合には、ローンを上回る分の住宅価格が清算価値として計上されることになります。
そのため、アンダーローンの場合には、住宅価格から住宅ローン残高を控除した額が高額になった場合、個人再生をしても、借金が減額されなかったり、減額されてもなお高額な返済が継続したりする結果となることが珍しくありません。
このような場合でも、再生計画が認められるだけの返済能力(履行可能性)があれば、個人再生をすることはできます。
もっとも、1か月当たりの支払額が高額になる可能性が高いため、かなりハードルの高い個人再生となることが予想されます。
4 住宅ローン特別条項を利用しないという選択肢
なお、住宅がアンダーローンの場合、住宅ローン特別条項を使わず、住宅を手放したうえで個人再生をするという選択肢もございます。
この場合、住宅を売却して住宅ローンを返済した後に残る住宅ローンは、その他の債権者と同じように個人再生の再生債権者の一人として扱われることになります。
住宅ローンを再生債権者に含めるのであれば、住宅ローンについても返済をストップしたうえで減額の対象とすることができるため、再生計画が履行できる可能性は高くなります。
ただし、住宅ローンは高額であることが多いため、住宅ローンの残額を再生債権に加えると債務額が5000万円を超えてしまうというような場合には、個人再生をすることができなくなってしまいます。
個人再生をしたことは家族に知られるのですか? できるだけ自己破産はしたくないのですが?