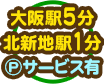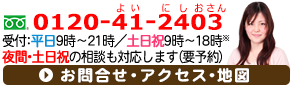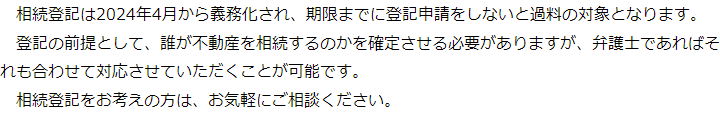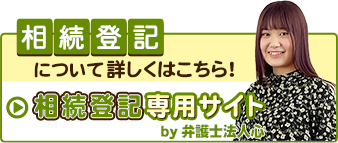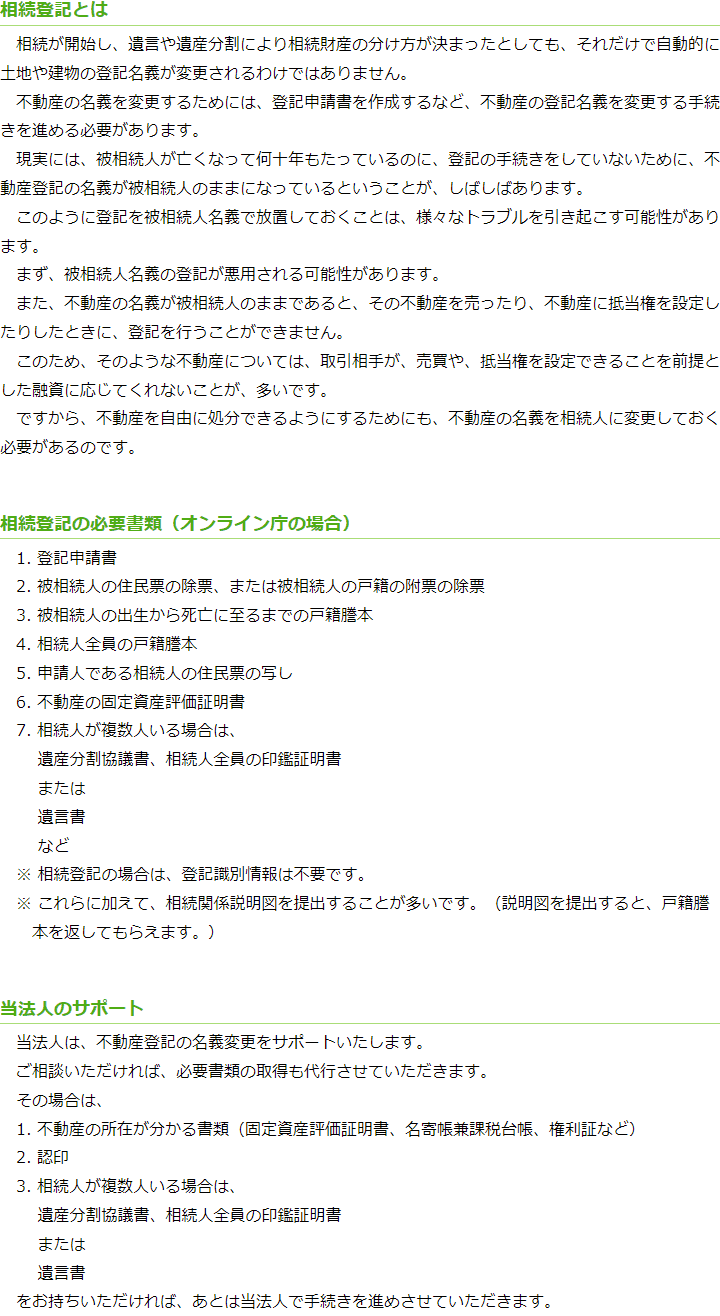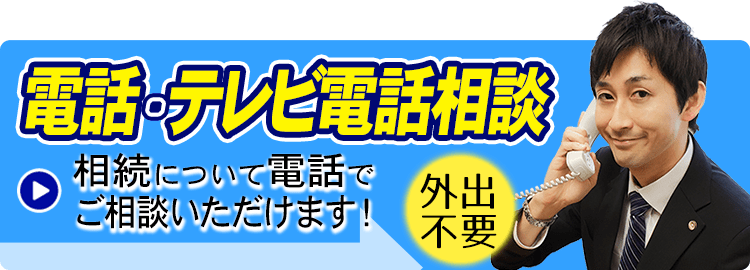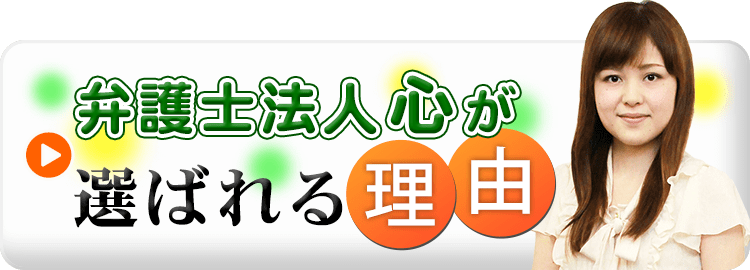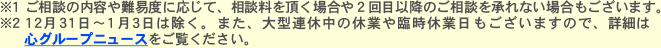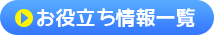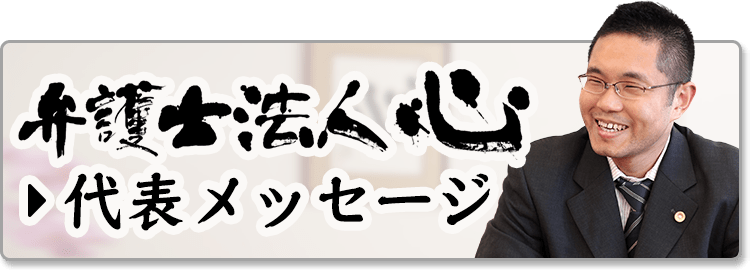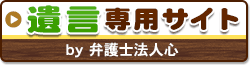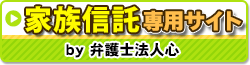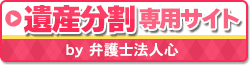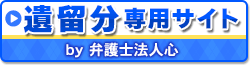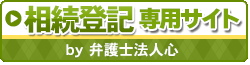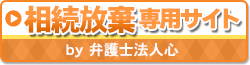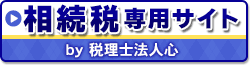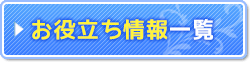相続登記
すぐに相続登記をしておいた方がよい理由
1 相続登記とは

相続登記は、相続を原因として、被相続人から相続人に所有権が移転することを内容とする登記を言います。
相続登記をせずにいると、以下に述べるようなデメリットがありますので、相続登記はすぐにしておいた方がよいと言えます。
2 相続人の権利が主張できなくなります
そもそも登記には、所有権をはじめとする権利関係の来歴及び現況について、正確に記載されるべきであるとされています。
にもかかわらず、相続人が被相続人から不動産を相続することになったのに、その結果を反映させないでいると、その不動産に関する相続人の権利を主張することができなくなります。
例えば、相続人がその不動産を売却したり、担保にしたりすることができなくなります。
3 時間が経過すると相続登記が困難になります
また、相続から時間が経過すると、相続人も代替わりして、相続人の相続人が増えていくことになります。
例えば、相続が発生してから何十年もたった後で、相続登記の手続をしようとしても、関係が希薄な相続人が多数になり、手続をしようにも話がまとまらないことはもちろん、そもそも、対象となる相続人を調査して見つけること自体が困難になることになりかねません。
4 取得した権利を失う可能性があります
相続人が遺産分割や遺言によって取得した不動産のうち、法定相続分を超える部分については、その旨の相続登記をしなければ第三者に対して権利を主張することができません。
例えば、相続人A、BのうちAが、遺産分割協議により単独で不動産を取得し、相続登記をする前に、相続人Bの債権者が不動産を差し押さえた場合、Aは、法定相続分を超える部分について、不動産の所有権を失うことになります。
5 相続登記の法的義務化
従来、相続登記をすることが法的には義務になっていませんでした。
しかし、相続登記をしないことによるデメリットは以前から問題になっており、その対応として、国は不動産登記法を改正しました。
それにより、令和6年4月1日以降、不動産を相続した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
このように、国は、相続登記を法的義務にし、相続登記をすぐに行うようにさせています。
相続登記の流れと必要な期間
1 相続登記の対象となる不動産の確認

相続登記は、相続を原因として、被相続人から相続人に所有権が移転することを内容とする登記のことを言います。
相続登記をするに当たっては、まず相続登記の対象となる不動産があるか確認する必要があります。
被相続人の不動産は、遺言書があれば、その遺言書に対象となる不動産が記載されていることがあります。
また、遺言書がなかったり、遺言書に不動産の記載がなかったりした場合、被相続人宛てに届いている固定資産税評価証明書に記載された不動産を確認する方法もあります。
実際に被相続人の名義となっているのかについては、その不動産の登記簿を取得して確認する必要があります。
不動産の登記簿を確認して、権利者の欄に被相続人が所有者として記載されていれば、相続登記の対象となると考えてよいでしょう。
2 戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の準備
対象の不動産が確認できたら、相続登記に必要な書類を準備します。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、誰がどのように不動産を取得することになったのかが記載された遺産分割協議書が必要になります。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人と被相続人との関係に応じて、各相続人の現在の戸籍、遺産分割協議書に押印した実印の印鑑登録証明書等の書類が必要になります。
遺言書がある場合には、登記の原因が相続を原因とするものなのか、遺贈を原因とするものなのかによって、必要な書類が変わってきます。
その他、新たに登記の名義人となる方の住民票や、登録免許税を計算するための固定資産評価証明書などの書類が必要になります。
3 法務局への申請書類の提出
必要書類が揃ったら、法務局に相続登記の申請書類を提出します。
申請の際、作成した申請書とともに、計算した登録免許税の額に応じた収入印紙も貼付して、申請書類を提出します。
どの法務局に申請書を提出するのかは、対象となる不動産がどこにあるのかによって管轄が異なります。
4 相続登記に必要な期間
相続登記に必要な期間は、戸籍等の必要な資料を収集する期間のほか、相続登記の申請をしてから登記が完了するまでの期間によっても左右されます。
申請をしてから登記が完了するまでの期間は、大阪法務局のホームページで「登記完了予定日」として公表されています。
参考リンク:大阪法務局・登記完了予定日
合計すると、1か月から2か月程度を見ておいた方がよいと思います。