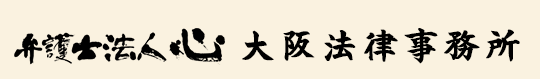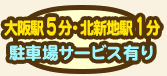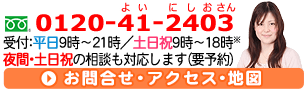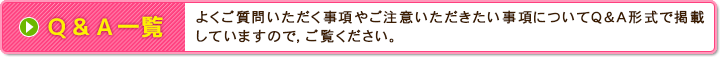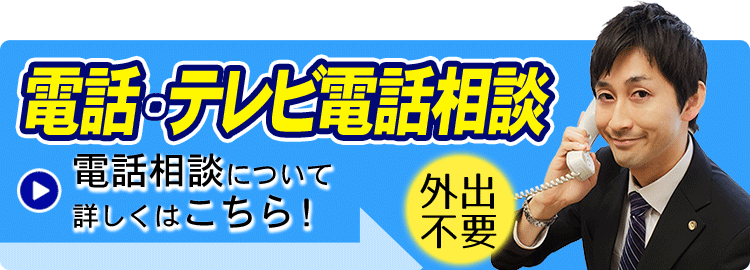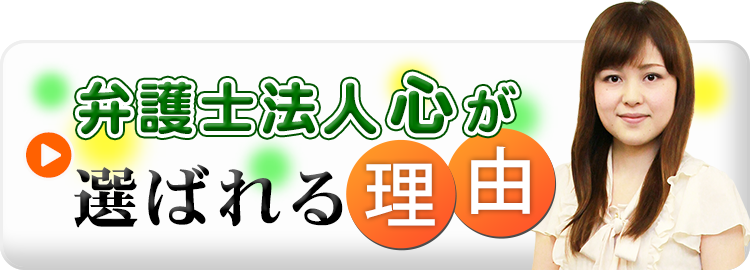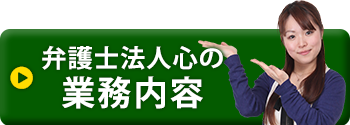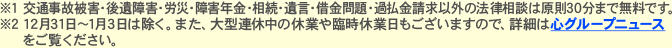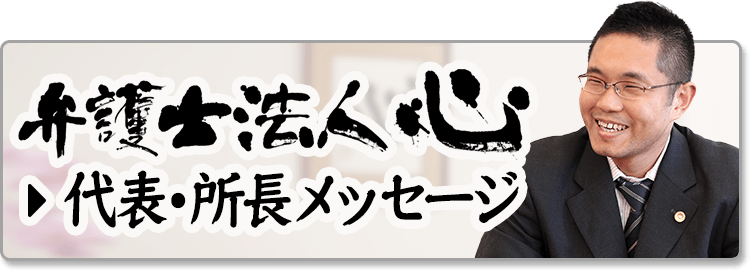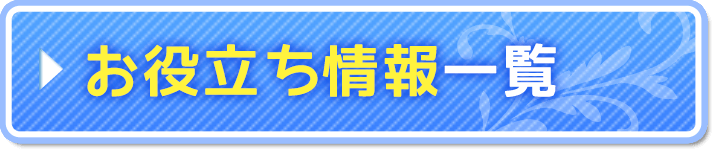発達障害で障害年金が受け取れる場合
1 発達障害は精神の障害として障害年金の支給対象となります
発達障害は、障害年金制度のなかでは精神の障害に分類され、様式120号の4の診断書を年金事務所に提出して審査を受けることができます。
参考リンク:精神の障害用の診断書を提出するとき
この診断書の内容を年金事務所が判断して、障害の程度が、障害年金の支給対象となる程度に達していると認められ、その他の年金納付要件や年齢的な要件をみたせば、障害年金を受給することが可能となります。
2 精神の障害の場合にどの程度の障害があれば障害年金を受給できるか
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、精神の障害の場合、症状の程度と年金が支給される等級の関係は以下のとおりです。
- 1 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、か つ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とするもの
- 2 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
認定基準の文章を読んだだけでは、イメージがつかみにくいかもしれませんので、あえて大雑把な目安でご説明します。
「日常生活には大きな支障はないけれど、仕事をしようと思うと制限がある(支障が大きい)」という程度が3級、「仕事だけでなく、日常生活を送るのにも支障が大きくて誰かのサポートがないと、普通に生活することが難しい」という程度が2級、「仕事はもちろん、一人では日常生活を送ることも不可能で、常に誰かが横について面倒を見ていないと生きていけない」という程度が1級のイメージになります。